こんにちわ、ぜつえん(@zetuenonly)です!
2年前にテンカラ釣りを始め、今年で3年目です。
最近では夏は山よりキャンプよりテンカラが多くなってきています。
今年からタイイング(毛ばりを自分で巻くこと)もするようになったので、一度知識のおさらいをしようと思ったところで、割引セール期間にAmazon Kindle Unlimited(アマゾンキンドルアンリミテッド)に入っていたことを思い出しました。
キンドルアンリミテッドは数十万冊の本が読み放題になる月額サービスです。
今回はキンドルアンリミテッドの中からテンカラに関係する本を9冊読んだのでオススメの本を紹介していきます。
アウトドア本の全般オススメと詳しくは別記事で紹介しています。
スポンサーリンク
趣味を本で学ぶ理由
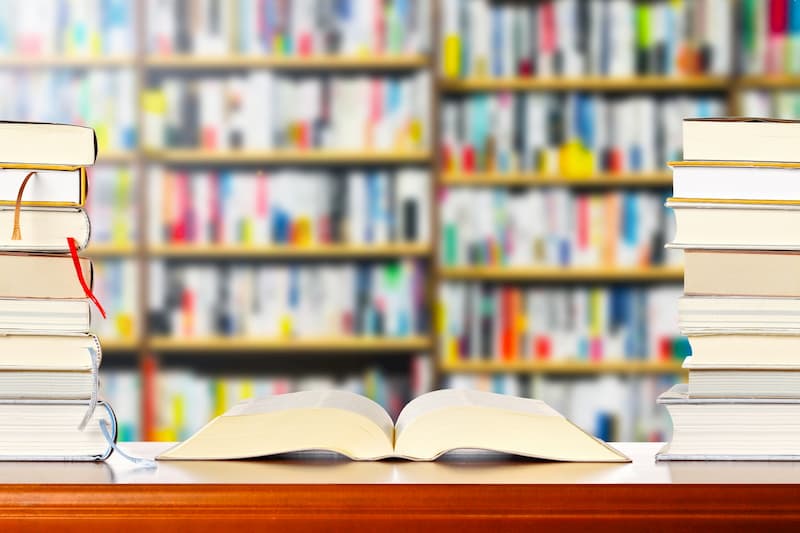
いまやブログやYouTubeなど無料で数多の情報が手に入ります。それなのになぜ本で学ぶのかという話。
趣味を本で学ぶ時のメリットとしては、基礎を飛ばさずに知れること。これが一番だと思います。
長くアウトドアの山やキャンプをしている人でも必要がないからと基礎的な知識に欠けてる人は珍しくありません。
それが悪いというわけではないのですが、基礎を知ることは応用力に繋がり、遊びの幅を広げてくれます。
基礎知識は無くてもいいけど、有るならあったほうが良いモノだと思っています。
ブログやYouTubeでは実際のイメージがしやすく、個人の応用力を見れるメリットはありますが、個人が作っているコンテンツのため、順序だてて教えてくれるというのは稀です。
そして、見たいとこだけ見ることが多くなり、そのため好きじゃない、面白くないという理由で基礎は飛ばされがちですし、見る側も飛ばしがちになります。
長く遊ぶアウトドア趣味において基礎を学ぶというのは後々生きてくるシーンは必ずあります。
その“基礎知識”を余すとこなくまとめられていて、1冊で完結するという所から、基本を学ぶのに優れたコンテンツが本だと思っています。
ブログ、動画、本、どれが優れているという話ではなく、情報収集のしやすさにおいて向き不向きがある、そういう話です。
今回はテンカラ初心者なぼくがテンカラ本から情報を得てふむふむなるほどなーとなった本の感想を書きながらオススメしていく記事です。
スポンサーリンク
キンドルアンリミテッド
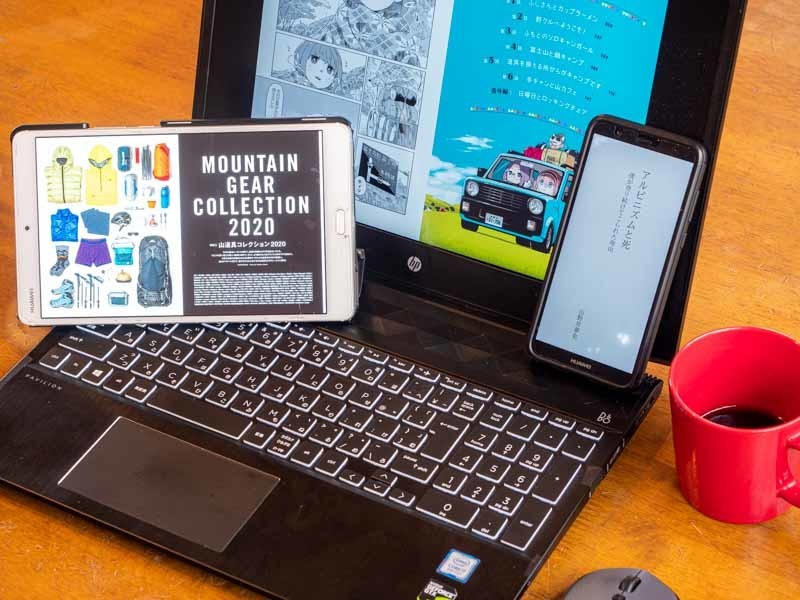
アマゾンが提供する月額制の電子書籍読み放題サービスがキンドルアンリミテッドです。
月額980円でスマホ、タブレット、パソコンどの端末でも電子書籍で本を読むことができます
コミック、雑誌、小説、書籍など幅広く読むことができ、アウトドア好きな方なら雑誌だけで元が取れるラインナップがそろっているのが魅力です。
今回のように新しい趣味をしっかり学ぼうと思った時に入門書をかたっぱしから読みあさることができるのもキンドルアンリミテッドの魅力的な使い方です。
詳細は別記事で→月額980円Kindle Unlimitedで本読み放題!アウトドアのオススメ本を紹介!
30日間無料お試しの登録は下からどうぞ!
スポンサーリンク
オススメのテンカラ本と感想
テンカラというワード自体が希少で、本の数がそもそも多くありませんでした。
その中からさらにキンドルアンリミテッドの読み放題対応となるとさらに少数。
読んだ中から感想、若干の内容、そしてオススメを紹介していきます。
名手に学ぶ テンカラ釣りの極意50

テンカラ本の1冊目にオススメなのがこれ!
テンカラを始める前、初めてすぐ、釣れないなと思った人に読んで欲しい内容でした。
テンカラ四天王と呼ばれる名人4人のQ&Aを踏まえながら、同じシーンでの名人達の思考の違いを知ることができます。
序盤の基本ではテンカラとは、から始まり魚の種類や特徴、毛ばりの種類竿の握り方、キャストの仕方、流し方、釣りのルールまでをしっかり記載してくれています。
そこから道具の種類と選び方に入ります。釣り具から服装まで、竿の種類とひたすらに熱い名人達の竿の選び方。
そのあとに極意50に入ります。
・覚える結びは3つでいい
・春は小さく、夏は大きく(針のこと)
・ヤマメはさらっと、イワナはしつこく
・緩い流れを狙え
といった定番からテクニック、タイイングなどを50個紹介しています。
写真と図解、名人の一言があって始める前の基礎知識から知識に深みを持たせるとこまでしっかりとあり入門~初級者向けの内容です。
強いて言うなら、50の極意が白黒ページなのがもったいない。渓の写真が深さなどわかりにくいのでカラーなら見やすく読みやすくわかりやすくなったと思います。
それでも内容的にはとても詳しくわかりやすい、それでいて実用的。テンカラ初心者には最初に読んで欲しい1冊です。
山釣りJOY

テンカラ本で面白すぎてバックナンバーまですべて読み切ったのがこの山と溪谷社が出す山釣りJOY。
山×釣りを題材にした本誌が、ぼくのテンカラスタイルとマッチしていて参考になる部分も多く、釣行のグレードも高く質も高い記事、なにより行きたいと思わせてくれる内容に惹かれました。
初心者向けではなくむしろ中~上級者向けな宿泊想定の釣行が多く、憧れの山釣りにいったレポートを著名な山屋やテンカラ師がしてくれてます。
テンカラ、餌、ルアー、フライと釣りスタイルは様々。
見るからに最先端でハイエンドな装備選定から年季の入った装備まで紹介もあり、アクセスが全てでクライミングスキル無しではたどり着けない渓でのイワナ達に胸が躍ってしまいました。
2017年から始まった年刊紙でまだ4冊目。すべてキンドルアンリミテッド対応なのも嬉しい。
良すぎたので数冊分を別々に感想を書いていきます。
山釣りJOY 2020 vol.4
2020年最新号、少し前はアンリミテッド対応してませんでしたが、最近対応してました。
まず道民として驚いた、奥尻島へのイワナ釣行。
結果的に物凄く数は少ないという話でしたが、調べてもわからなかったから行ってみた、という釣り人の飽くなき好奇心を感じれる内容でほんと好き。ってなりました。

後半の特集「源流装備入門」道具の種類や選び方の基本がわかります。濡れるウェア、泊想定なテント寝袋から竿、沢靴まで十数ページにわたった大ボリュームです。
その沢靴カタログページでキャラバンの広報の方の話。
「フェルトラバーの寿命の目安は3年、13mmフェルトなら7mm程度が寿命」なるほど。
「沢靴はピッタリめがいい、岩場を登るときにずれにくいから」なるほど。
この人の話は数ページにわたり沢靴一覧と一緒にシューレース、メンテなどもあってすごい参考になります。
最後の半世紀も沢へ生き続けている豊野則夫さんへのインタビュー記事。
一生をかけて遊ぶ趣味として釣りや山、キャンプを考えさせられる内容です。読むことで先を見据えて持久力のあるアウトドアを意識できます。
山釣りJOY 2019 vol.3
2020がつい最近までキンドルアンリミテッドになってなかったので、2019を何周かしてしまってました。
山釣りドキュメント②で南会津釣行する森山伸也さんの話がテンカラっぽくて好きです。
釣りが上手くないから足で稼ぐ、という表現。
スタートから山頂を踏んで、鞍から沢へ入り下って1泊目。その先の合流点から沢を登るというアクセスで1日かかるコース。
でもその先はイワナ天国で釣れすぎて結局上手くならないという嬉しい話。
ぼくも人のいない渓で、警戒心も忘れたイワナを釣りたいテンカラなので、とても共感でき憧れるレポートでした。
後半パタゴニアxダナーコラボのウェーディングシューズの記事に「一説ではフェルトと歩行距離60km、ビブラムは200kmだとか」という記載。
フェルトのほうが弱いのはなんとなくわかりますが、正直かなり短い距離だなという印象。
ただ噂程度の書き方で明記ではないとの水中や林道かでも大きく変わるはずだとは思います。
2年ほど使った自分のフェルトシューズがヘタってきてるのでついついソールの話に目が行くようです。
あと最後の非カラーページの「僕はマムシに噛まれた」。
必然的に道なきコース外を歩くことが増える山釣りでは、動植物への注意も必要です。
マムシに噛まれてからの時間経過での指の様子が生々しい内容です。野生動物の住処に入っているという意識は忘れないようにしたいものです。
その他vo1~2も同様に楽しめる内容です。どちらも読み放題対象になっています。
釣りでは古いから役に立たない情報ということもないため比較的参考にしやすいでしょう。
つり人 2019年4月号

つり人社のだす月刊誌つり人の渓流特集で、サブタイトルが「渓流釣りQ&A」。
渓流釣り全般で、テンカラに重点は置かれてませんが、イワナヤマメがターゲット。
渓流釣りの基本を学ぶことはテンカラにも生きてきますし、ぼくはテンカラのときにも餌釣り用に5.4mの延べ竿を持っていきます。違う釣り方をできる可能性も容易できるため広い知識は生きてきます。
内容としてはかなりライトで、1ページに数個のQ&Aが足早に書かれています。
キャッチーな絵で図解されていて文字無しでも読み進めることができるほどです。
ヤマメとイワナ、それぞれの付き場は?
の項目では、上流域の写真からそれぞれの魚の特徴を意識したポイントの解説があります。
個人的にはここがこの本で一番良かった。
流れの中にいるヤマメと岩場に隠れるイワナ、その川にどちらの魚がいるかによって狙うポイントは変わってきます。それが意識できるようになりました。
中盤に6ページのテンカラの疑問を紹介するページがありここも参考になります。
後半は海などになってくるまで川は中盤までです。
必読ではなく、基本を丁寧に学べる内容でもありませんが、小さな疑問はいくつも解決するという意味で一度は目を通したい本です。
渓流釣りのすべて

タイトルに反して、テンカラのテの字も出てこないのが渓流釣りのすべて。
テンカラは渓流釣りと違うんか!?と思ってしまいながらもだらだら読み進めていきました。
非カラーページの後半で餌釣りの項目からポイントの流し方、狙い方が本編。
渓流でルアーなら価値のある本ですが、”テンカラ”を知りたいなら読む必要はあまりない本。
渓流釣り

サバイバル読本などを出している笠倉出版社の年刊誌「渓流釣り」
釣行レポートをメインにしている辺りが山釣りJOYと似た本。
しかし山釣りJOYの後に読むと写真の質の低さ、源流よりは上流域に近いライトな釣りに見劣りを感じてしまう内容なのは否めません。
後半には渓流釣り入門者向けのポイントの狙い方、道具の選び方もありますが、ボリュームは小さく満足感は得られませんでした。
関東から行きやすい川のピックアップが多いようで、関東の山釣りをしたい人にとっては川選びにいいかもしれませんが、源流に行きたい道民には魅力の薄い本。
タープの張り方火の熾し方-私の道具と野外生活術/高桑 信一

「源流」と「テンカラ」を考えた時に欠かせない人物が高桑信一さん。
著書源流テンカラはあまりにボリューミィで気軽に手が出せませんが、このタープの張り方火の熾し方は写真や図が半分、文字半分で比較的読みやすい本です。
沢登りや源流釣行ではタープ泊で直火での焚き火が一般的です。
そこにテンカラが混ざったスタイルでの道具の選び方や考え方、テクニックなどを細かく写真付きで書いてくれています。
全体的に装備のチョイスが少し古く、直接的に参考にならない部分や今からこのスタイルを目指すのも違う部分も多くあります。
それでも効率に走らない趣味を意識でき、自然に感謝をして山で、川で遊ぶということを考えなおすことができると思います。
そのため決して初心者向けの内容ではありませんが、源流泊釣行をしている、目指している人にはお勧めしたい一冊です。
最新の軽量な道具、効率的な道具、それもいいですが、しょせん釣りも山もキャンプも遊びです。効率よりも大事なモノがあるということをわからせてくれるでしょう。
スポンサーリンク
テンカラ釣りで思うこと

1冊目の「名手に学ぶ テンカラ釣りの極意50」から得た部分が大きいですが、テンカラで魚を釣るために大事なことは川選びです。
適切な毛ばりなら多少の種類の違いに大きな差はないということ、釣れない場所では釣れないということ、道具で釣れる釣れないの差は出にくいということもわかりました。
どの川がいいかは難しいですが、人の入らない、アクセスしにくい山奥の川ほど釣れます。
またテンカラで釣れる場所なら餌でもルアーでも釣れます。
技術的な問題もありますが、同じ川同じ場所でも、体感で餌釣りはテンカラの2~3倍は釣れます。

ではなぜテンカラをするのか?
理由は簡単。テンカラは楽しいからです。
色んな本でも出てきますが、テンカラの一番の魅力は魚が水面を割って毛ばりに食いつくシーンが見れることでしょう。
他の釣りではなかなか得られない楽しさで、釣り人と魚との距離をずっと近くに感じられます。
これは何度か経験すればわかってきます。同じ場所でエサで釣るよりもテンカラで釣ったほうが2倍は楽しいからです。水面を割って食いつくヒットにはついついにやけちゃいます。
さらに加えると、仕掛けがシンプルなことによる軽量コンパクトさ、重りがないことによるライントラブルの少なさによるストレスフリー、キレイな渓流を釣り歩く楽しさなどでしょう。

テンカラ釣りを3年目に突入して思うのは、魚を釣りたいならエサ釣りをするべきだし、道具や引きを楽しみたいならルアーにするべきだと思います。
テンカラにしかない魅力、それに気付けるならテンカラはとても魅力的な釣りになるのではないかと思います。
まとめ
もうまとめきちゃった感あってまとめに書くことないのはあるあるです。
テンカラの本を読んでて思うのは本が好きなんだなぁということ。活字を読むのは楽しいですね。
逆に動画は苦手で、時間に対して得られる知識量の少なさと動く映像からくる情報量の多さからです。明確に欲しい情報がいつどこで得られるかわかりにくいのもあります。
好き嫌いに過ぎずどちらを否定するわけでもないですが、偏らず用途に適した情報収集ができるというのも一つのスキルでしょう。
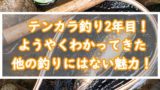

スポンサーリンク



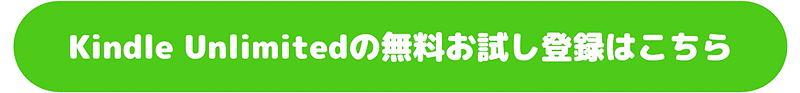









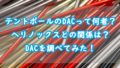
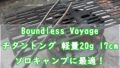
コメント